『自閉症の僕が跳びはねる理由』、著者である東田直樹さんはなんと会話のできない重度の自閉症です。パソコンおよび文字盤ポインティングによってコミュニケーションが可能なんだとか。
『自閉症の僕が跳びはねる理由』を執筆した当時は13歳。自閉症の方本人の言葉で、気持ち・支援してほしいことが書かれているんです。
自閉症の方について疑問に思うことについての答えが、一問一答形式で書かれています。
自閉症について勉強しよう!そう思ったとき、手にする本やネットのページは支援の専門家が書いたものが多いのでは?
支援者ではなく、自閉症当事者の言葉で自閉症について知ることができる。
そんな本はあまりなく、貴重ですよね。
また、28か国30言語で翻訳され、世界的ベストセラーになっているんだとか。
ということで、子どもが自閉症と診断されたという保護者の方はもちろん、
学校の先生や保育関係の先生にもぜひ読んでほしい一冊です。
Amazon Kindle では、サンプルをダウンロードすれば目次や“1 筆談とはなんですか?”“2 大きな声はなぜ出るのですか?”を読むことができます。
漫画版もあります。
以下からのレビューは、主に教師や保育士としての目線で書いています。
我が家の次男は発達ゆっくりさんで、同年齢の子どものようにはコミュニケーションがとれません。
『自閉症の僕が跳びはねる理由』の内容に当てはまるところもありましたが、次男は自閉症と診断されているわけではありません。
ということで、今回のレビューは保護者目線ではなく、支援者目線で書くことにしました。
本ページではアフィリエイト広告を利用しています
『自閉症の僕が跳びはねる理由』を読んでよかったところ
重度の自閉症の方本人の気持ちが知れる
先生という職業をしている限り、
相手(子ども)の立場になって、気持ちに寄り添って
というのはよく言われると思います。
私たちはおそらくできるだけ本人の気持ちに寄り添った支援を心がけています。
しかし、それが本当に正しいのか?そう思えました。その文がこちら。
普通の人は気持ちが苦しくなると、人に聞いてもらったり、大騒ぎしたりします。
僕たちは、苦しさを人にわかってもらうことができません。
パニックになっても、大抵見当違いのことを言われるか、泣きやむように言われるかのどちらかです。
苦しい心は、自分の体の中にため込むしかなく、感覚はどんどんおかしくなってしまうような気がします。
P.74 29 みんながしないことをするのはなぜですか?体の感覚が違うのですか?より
みなさんも経験がありませんか?
自閉症の子がパニックなったとき、落ち着いてもらうために、気持ちを代弁するような言葉がけをする。
自分は寄り添っているつもりだが、自閉症の方本人が納得している様子はない。
こんなときに自閉症の方はこのように上記のように考えていたのだと発見できました。
このようなことを減らすために、筆者のように自らの想いを伝える方法を支援していくことが重要だと感じました。
著者の当てはまらないところははっきり書いてくれている
私たち先生は自閉症の方と関わるとき、本などで勉強しませんでしたか?
その本には“自閉症によくみられる特徴”が書いてあったことでしょう。
しかし、いざ現場にでてみると、その“自閉症の特徴”に当てはまる人もいれば、当てはまらない人もいる。
その違いというのに戸惑いませんでしたか?
一人ひとり違う人間なので、よく考えてみれば当たり前のことですがね。
例えば偏食についての文
自閉症の人の中には、決まったものしか食べられない人がいます。僕は、あまりそういうことはありませんが、食べられない人の気持ちは少しわかります。
1日3回、同じ食べるという行為を繰り返すわけですが、色々なメニューが苦痛なのかもしれません。
P.77 31 偏食が激しいのはなぜですか?より
筆者自身には当てはまらないところははっきり書いてくれるが、偏食をもつ人の気持ちを代弁してくれている。
この著者と会話しているように思える書き方のおかげですごく読みやすいんです。
一般的な自閉症に関する本にはあまりないのでは、と思います。
読んでためになった項目
ここからは、私が『自閉症の僕が跳びはねる理由』をよんで、心に残った、ためになったところをお伝えしていきます。
3 いつも同じことを尋ねるのは何故ですか?
こちらの項目には、“同じことを繰り返し聞くという行動”の理由の一つに、
言葉遊びができること をあげられています。
僕たちは人と会話することが苦手です。どうしてもみんなのように、簡単に話すことができないのです。
けれど、いつも使っている言葉なら話すことができます。それが言葉のキャッチボールみたいで、とても愉快なのです。
P.19より
我が家の次男は言葉の発達が実年齢より遅れている状態です。
4歳を過ぎて、言葉のキャッチボールができるようになってきました。
自閉症と診断されているわけではないのですが、最近同じことを何回も聞くんです。毎日どころか1時間に一回は同じことをきいてきます。
我が家の次男も言葉のキャッチボールを楽しんでいるのかな?と思いました。
6 小さい子に言うような言葉使いの方がわかりやすいですか?
僕たちだって成長しているのに、いつまでたっても赤ちゃん扱いされます。
(中略)
赤ちゃん扱いされるたびに、みじめな気持ちになり、僕たちには永遠に未来は訪れないような気がします。
本当の優しさというのは、相手の自尊心を傷つけないことだと思うのです。
P.23より
私たちも、必要以上にできないやつ扱いされるのは嫌ですよね?
難しい言葉をつかって話してほしい、というわけではなく、年齢相応の態度で接してほしいそうです。
自尊心を傷つけないような接し方ができているのか、改めて考えさせられますね。
46 自由時間は楽しいですか?
「好きなことをしてもいいよ」
と言われたとします。けれども、好きなことと言われても、何をしたらいいのか探すのは大変です。そこに、いつも使っているおもちゃや本などがあれば、それで遊びます。でも、それは自分の好きなことではなくて、できることなのです。(中略)それをみて、みんなは(これがしたいんだ)と思うのです。
P.108より
私自身これに当てはまるような体験をしたことがあります。
特別支援学校の空き時間に、ある自閉症の子に担任の先生がその子が普段よく使っているおもちゃを渡しました。
その自閉症の子も普段から遊んでいるおもちゃなので、遊び方には慣れている。
でも、その子の様子を見ると、(本当に楽しんでいるのかな…?)と思ってしまいました。
もしかしたらその自閉症の子も、好きなおもちゃではなくできるおもちゃを使っていたのかもしれない。
その子の本当に興味があるのは何か、もっとじっくり考える必要性を感じました。
東田直樹さんのその他の著書
自閉症の僕が跳びはねる理由2
あるがままに自閉症です(エスコアール)
跳びはねる思考(イースト・プレス)
自閉症の僕は七転び八起き(KADOKAWA)
詩集 ありがとうは僕の耳にこだまする(KADOKAWA)
東田くん、どう思う?自閉症者と精神科医の往復書簡(KADOKAWA、山登敬之と共著)
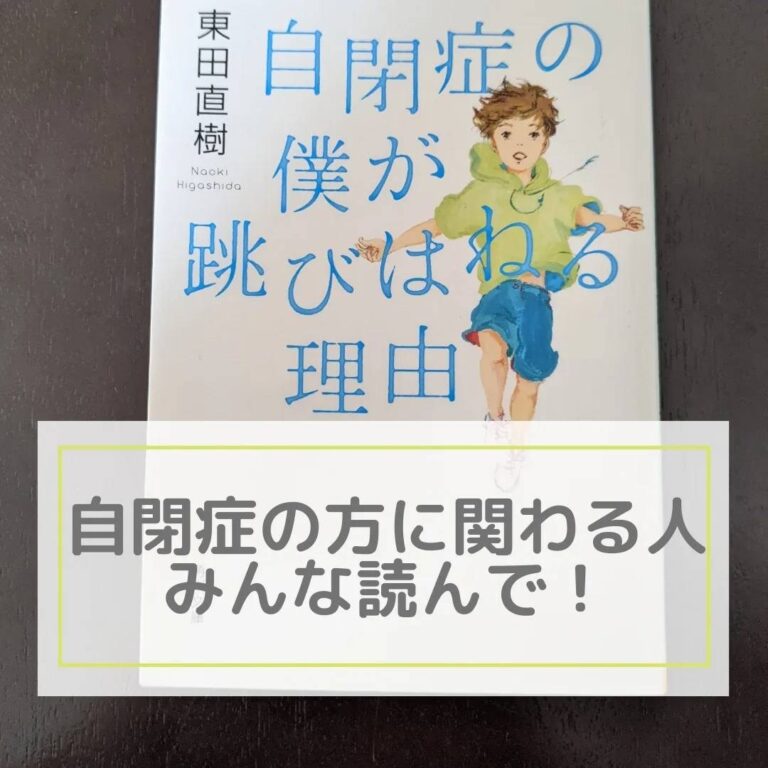
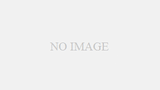

コメント