障害のあるお子さんを育てている皆さん、毎日お疲れ様です。
我が家には、発達がゆっくりで、現在小学校の支援級に通う息子がいます。
かわいらしい笑顔を見るたびに「頑張ろう」と思える一方で、ふとした瞬間に
「私ばかり…」
「将来はどうなるんだろう」
と不安になることはありませんか?
私も、同じように感じています。
そんな時に出会ったのが、この本です。
「どう生きていけばいいんだろう?」その答えがここに
この本は、『障がいのある子どもを育てながらどう生きる?』。
著者の黒川直樹さんは、知的障害のある成人したお子さんを育ててきた方です。幼少期から成人後まで、子育て中に「やってよかったこと」や「考え方」が具体的にまとめられています。
この本を読んで、私は「この先どうすればいいんだろう」という漠然とした不安が少し軽くなり、親としてどう生きていけばいいかのヒントをもらいました。
今回は、私が特に「これは!」と共感した2つのポイントを紹介します。
- 親はまず自分を大切にする
- 「親にしかできない支援」以外はプロに任せる
今、少しでも育児に疲れを感じていたり、この先が不安だったりする方は、ぜひ読み進めてみてください。
親が元気でいることが、子どもにとって何よりの安心
障害のある子どもを育てていると、「子どものためなら何でもしてあげたい」という気持ちから、自分のことを後回しにしてしまいがちですよね。
もちろん、子どものことは何よりも大切です。でも、こんな話を聞いたことはありませんか?
飛行機事故が起きたら、子どもより先に親が酸素マスクをつける。親が倒れてしまっては、子どもを守ることができないから。
障害のあるお子さんとの生活は、もしかしたら一生続くかもしれません。親が元気でいることこそが、お子さんにとって最大の「安心」になります。
毎日、育児で精一杯な方も多いでしょう。目を離せない時間もたくさんありますよね。私も同じです。
でも、ほんの少しの時間でもいいので、自分の心がホッとするような時間を作ってみませんか?
たとえば、私が実際にやっているのは、こんなささやかなことです。
- 家事の合間に好きな音楽をかける
- 温かい飲み物を用意しておく
- キッチンの隅でこっそりお菓子を食べる
- イライラしたら、潔くレトルト食品に頼る
美味しいものを食べることも、気分転換になりますよね。
「親にしかできないこと」以外は、どんどん頼ろう
この本では、「親だけができること以外はアウトソーシングする」ことを強くおすすめしています。
たとえば、放課後等デイサービス(放デイ)や学習塾、外来リハビリなど、プロに任せられる部分は専門家を頼るのが賢明です。プロの力を借りることで、親の心の負担も軽くなります。
この考え方を知ってから、私も以前は不安に思っていた放デイに、前向きに子どもを送り出せるようになりました。
逆に、親にしかできない支援とは何でしょうか?
それは、愛情をたっぷり注ぐことや、家を安心してくつろげる場所にしてあげることです。
これらは、親にしかできません。
親以外にもできる支援は、どんどんアウトソーシングして、自分自身と子どもに向き合う時間を大切にしましょう。
さいごに
この本には、親の生き方を考えるための具体的なヒントが52個も掲載されています。
もし今、「少し疲れているな」「この先どうしたらいいんだろう」と感じているなら、ぜひ一度手に取ってみてください。きっと、心が軽くなるきっかけが見つかるはずです。
この本から、あなたの「ヒント」が見つかりますように。
リンク
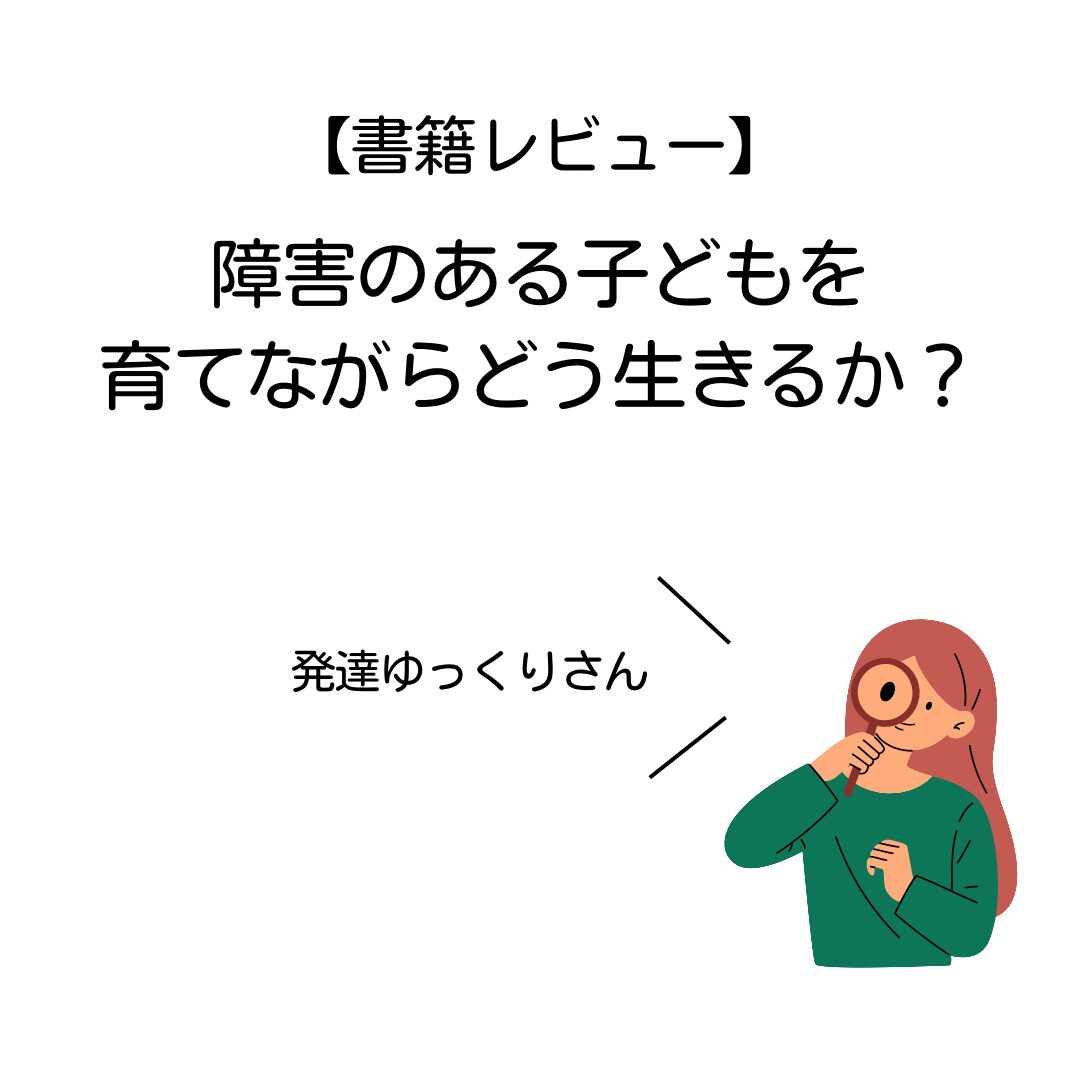


コメント